今回は、私が同僚の仕事を手伝って失敗した話を書いていきます。
人の仕事を手伝うって、サラリーマンにとっては当たり前のように思いますよね。
しかし、注意しないと同僚との関係悪化につながるという事を身をもって体験したので、これを学びに変えて共有してきたいと思います。

ほんとうに注意したほうがいいですよ
【体験談】私が同僚の仕事を手伝って失敗した話

私は勤続10年以上、同僚のAさんは年齢こそ近いものの入社してまだ数年の社員です。
Aさんは仕事のペースが遅く、自分の仕事が終わらないので、残業したり休日出勤を繰り返しています。
以前にAさんの職務を経験したことのある私は、そんなAさんを見かねて手伝うことにしました。
手伝い方としては、1ヶ月の中で忙しい日は決まっているので『〇日と〇日の〇時間だけ〇〇を手伝う』といった具合です。
これを1年間ほど続けました。
1年前のAさんは、入社してまだ1年足らず。
当時の私は、高学歴であるAさんに対し『慣れてくれば仕事のペースが早くなり、手伝わなくても済むようになるだろう。』と安易な考えを持っていたのです。
『高学歴=仕事ができる』とは限らないとは分かっていたものの、なんの根拠もなしにAさんを信じてしまったのです。
しかし、1年たった今、Aさんは仕事のペースが全く変わっていません。
実はこの1年、手伝いをやめるタイミングを見計らっていましたが、あることに気づきました。
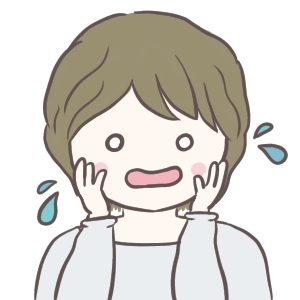
Aさんは、私が手伝うことを“当たり前”と思ってる?
Aさんからしたら仕事を手伝ってもらうことに対し、
ありがたい
ではなく、いつしか
あたりまえ
となっていたのです。
もちろん最初の数回は「ありがたい」と思っていたとは思います。
私は自分の仕事に余裕があるから手伝っているわけではなく、Aさんの残業している様子を見かねて やむを得ず 手伝っています。
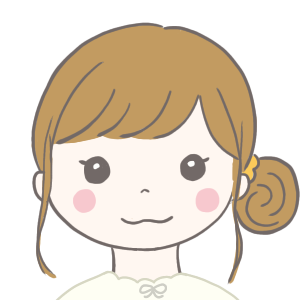
ここがお互いの認識のズレですね。
1年たったとき、私は自分の失敗に気づきました。

Aさんの仕事を安易に手伝った私が悪かった。。。
同僚の仕事を手伝う前に考えること3段階

1段階目:同僚の仕事が終わらない理由を考える

同僚の仕事が終わらない理由は何でしょうか?
3段階に分けて理由を考えてみましょう。
この場合、同僚がどうこうするのは危険です。
なぜかというと、そもそもの業務量が多い場合、手伝ったところで何の解決策にもならないからです。
業務量が多い場合は、上司なり人事なりに相談して増員するか業務分担の見直しをする必要がありますので、手伝うべきではありません。
ブラック企業でなければ、残業や休日出勤をしない終わらないほどの業務量なら、増員を計画するでしょう。
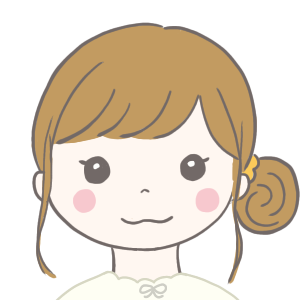
これに関しては、本人の問題ではないため、うまく増員できれば問題が解決されそうですね。
能力が足りていない場合は、どうしようもないですね。
その人に相当のポテンシャル(可能性)がなければ、手伝ったところで何の改善もされないでしょう。
この場合は本人のやる気が試されます。
やる気があるのかないのか、そこを見極めなければなりません。
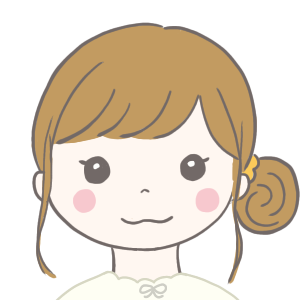
そもそもやる気があるなら手伝ってもらわなくても済むよう工夫するはずです。
これはとっても厄介なものです。
なぜなら、本人は怠けている自覚がない可能性が高いからです。
- 時間内に業務を完了させようとしていない場合
- やる気のない人
- 仕事をしているフリをする人

なまけ方にも色々ありますが なまけ癖 のある人は一番厄介ですね。
2段階目:同僚の仕事を手伝うときの判断材料3つ
手伝う前に考えくてはならないことは3つです。
先にあげた①~③をもとにして、仕事が終わらない理由を明らかにします。
- 業務量が多すぎる
- 能力が足りない
- なまけている
これらの混合パターンもあるので見極めるときには注意が必要です。
一番多いパターンとしては「①業務量が多すぎる」「③なまけている」でしょうか。
仕事の場合、友達ではないので得られるメリットを考える必要があります。
果に結びつかない業務は無意味(とまでは言いませんが…)だし、長期的に見た時に疲弊するのは自分自身です。
長く続けるには何らかのメリットが必要です。
ボランティア活動だって無一文では成り立ちませんから。
ここまで読んでいただけた方は想像がつくかもしれません。
自分判断で勝手に手伝うと痛い目にあいます。
手伝うときの手順としては、
- まず上司に相談
- 上司から依頼を受ける
ここで上司に相談する人は、「手伝ってもらう側/手伝う側」どちらでもOKです。
同僚からの依頼
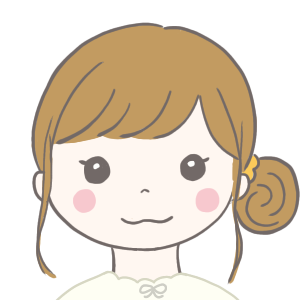
同僚からの依頼は受けちゃダメですね。
3段階目:手伝うか否かの最終判断
1段階目、2段階目とみてきたら、どうすべきかの判断が自分の中でできていると思います。
おさらいしてみましょう
- 同僚の仕事が終わらない理由を考える
- 同僚の仕事を手伝うときの判断材料3つ
- 手伝うか否かの最終判断
きっぱりはっきり最終判断を下しましょう。
上司からの依頼なら、手伝うという判断もあります。
しかし、自分の業務もあるはずですので、何かを手伝うなら何かを手放さなければならないこともあるかもしれません。
しっかりと上司へ相談したうえで判断しましょう。
もちろん、相談したうえで断るという判断もありかと思います。
これに関しては、いち社員が考える問題ではなく、会社側(上司や社長など)が考えるべき問題です。
さいごに

最後に、ひとつだけ注意することがあります。
それは

良い人はやめましょう。
もう一つ

無駄な優しさはやめましょう。
そして、大切なこと。
それは消して、人に冷たくする、という意味ではないんです。
客観的に思考した結果、そういう結論をだしたのですから、自信をもちましょう。
嫌われたくない、いい人と思われたい一心で無理に手伝ってしまうよりも、本音で向き合っている方がむしろ同僚との信頼関係が深まるはずです。



